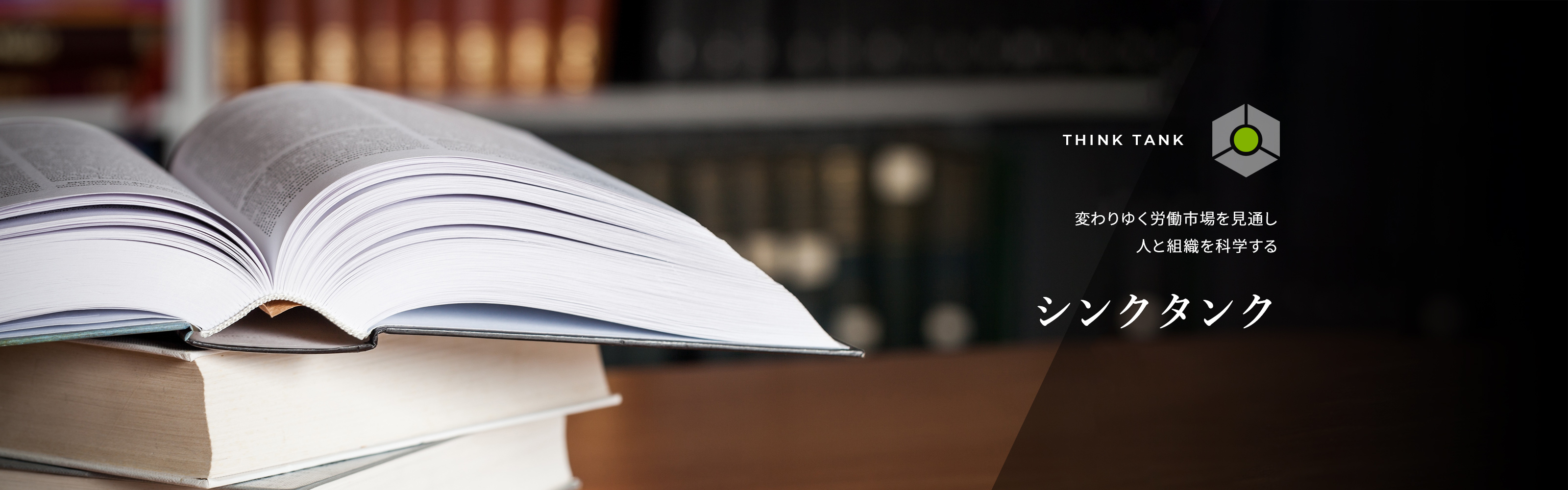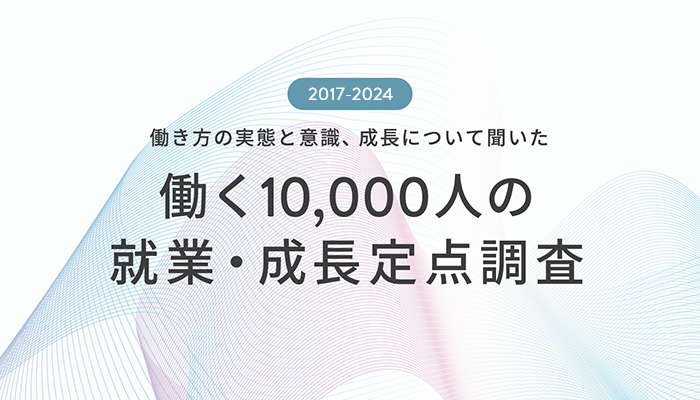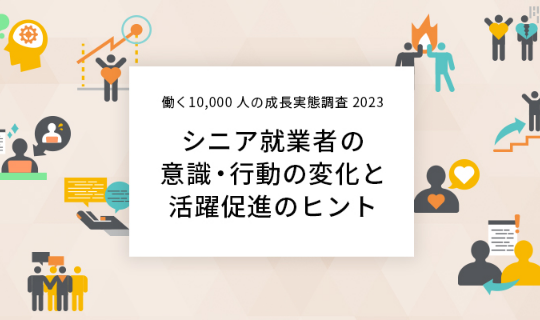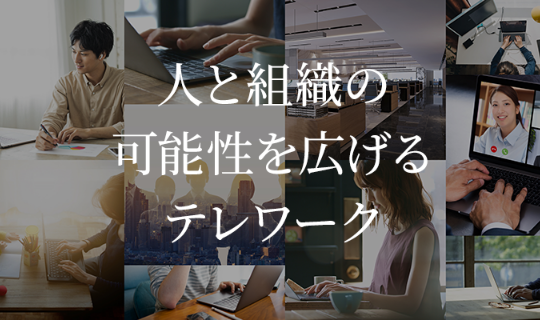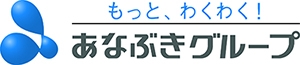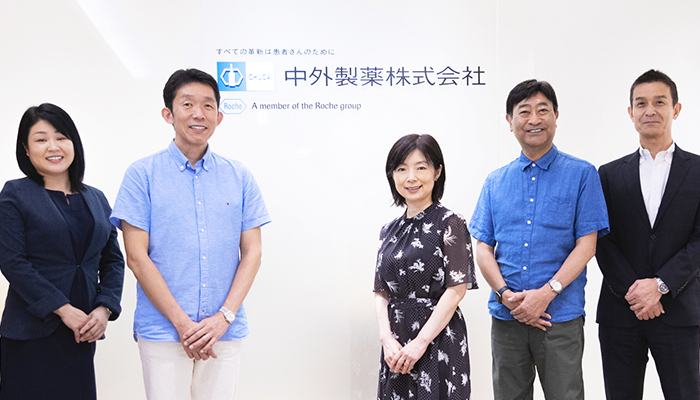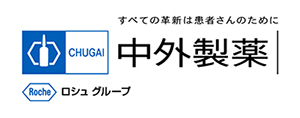Information
-
2024/3/27
2023年度版「調査研究要覧」発刊のお知らせ -
2023/11/2
キャリア自律セミナー2023(全6回)アーカイブ動画&イベントレポート公開のお知らせ
シンクタンク
実務に役立つ❝Deliverable❞な調査・研究から得た《知》を発信しています。
主なテーマ:
ソリューション
パーソル総合研究所は、人と組織、労働市場に関してあらゆる視点から調査・研究を行っています。
その調査・研究結果から得られた知見を活かし、「人と組織の躍進」をミッションとして、お客様に伴走しながら課題解決のためのソリューションをご提案します。
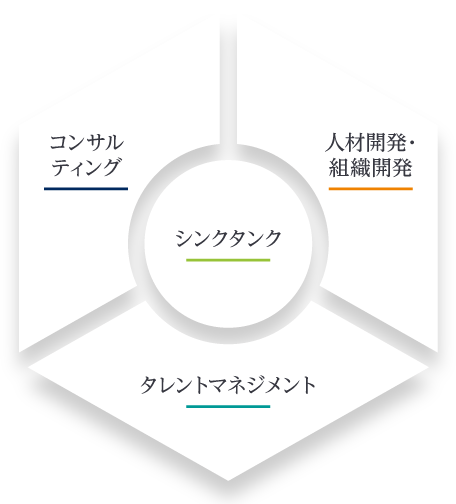
組織・人事変革を、総合的に支援
組織・人事コンサルティング人・チーム・組織の状態を
豊富なツール・手段で可視化
「人と組織の成長の要」となるマネジメント
人材の育成とリーダーシップの強化を支援
キャリア開発支援の仕組みづくり、
各年代の特性・課題に対応したプログラム
変化に強く、成果を上げ続けられる
営業組織とセールス個人を育てる
すべてのビジネス・パーソンに必要な
ポータブル・スキル習得を支援
ビジネスアナリシス